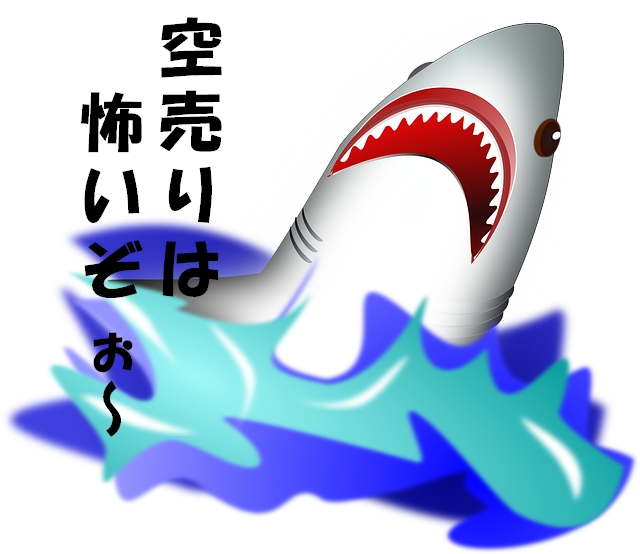株の売却方法まとめ|投資初心者が迷わない売り方と注意点を徹底解説

株を買った後に必ず訪れるのが「売却」の場面です。
しかし投資初心者にとっては、売り方ひとつ取っても「成行と指値の違いは?」「NISA口座で売るときは税金はどうなる?」といった疑問が多く、不安を感じやすいところです。
実際、株の売却方法にはいくつか種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。
売却の手順を理解していないと、思わぬ損失や機会損失につながることもあるため、売り方を正しく理解することは投資の基礎知識として欠かせません。
本記事では、
-
株の売却方法(成行・指値など注文方法の違い)
-
NISA・特定口座で売却する際の注意点
-
投資初心者がやりがちな失敗例と対策
をわかりやすく解説します。
この記事を読めば、「株の売り方」が整理され、安心して売却できるようになるはずです。
① 株の売却方法を理解する前に知っておくこと
売却=利益確定または損切りの重要なプロセス
株の売却は「買った株を現金に戻す」だけの操作に見えますが、投資において非常に重要なプロセスです。
売却によって利益を確定させたり、損失を限定したりできるため、どのように売るかが投資成果を大きく左右するといっても過言ではありません。
「買いは容易、売りは難しい」といわれるように、売却の知識を持たないまま投資を続けると失敗につながりやすいのです。
特定口座(源泉徴収あり)
売却益にかかる税金が自動で計算・徴収されるため、確定申告は不要です。
投資初心者やサラリーマンに最もおすすめの口座で、特に 毎年20万円以上の売却益がある人はこの方法を選ぶのがベスト です。
税金処理を自動で行ってくれるので、手間がかからず安心感があります。
特定口座(源泉徴収なし)
年間取引を自分で集計し、確定申告を行う必要があります。
節税や損益通算を目的に選ぶ人もいますが、取引量が多い場合はかなり手間がかかります。
基本的に初心者向けではなく、中級者以上が状況に応じて選ぶ方法です。
一般口座
現在では利用者は少なくなっていますが、すべての売買を自分で記録し、年間損益を計算して確定申告しなければならないため非常に面倒です。
税金処理の負担が大きく、初心者はもちろん経験者でも避けるべき口座といえます。
はっきり言って、一般口座は絶対におすすめしません。
NISA口座
売却益や配当が非課税になるメリットがあります。
ただし、非課税枠を使い切ると売却後に再利用できない、また損益通算や繰越控除ができないというデメリットがあります。
長期保有や資産形成を目的とする人向けの制度です。
同じ株を売却しても、口座の種類によって「手取り」が変わるため、仕組みを理解しておくことが重要です。
私個人の意見
私は税金処理が面倒なので 特定口座(源泉徴収あり) を利用しています。
自動で税金を処理してくれるため、確定申告の手間が省け、投資に集中できます。
特にサラリーマンで毎年売却益が20万円を超える人には、間違いなくこの方法をおすすめします。
逆に 一般口座はすべて自分で計算しなければならず、時間と労力の無駄 だと感じています。
「どの口座を使うか」で投資の快適さが大きく変わる──これは経験を通じて強く実感していることです。
② 売却注文の基本|成行と指値の違い
株を売却するときにまず選ぶのが 「成行(なりゆき)」と「指値(さしね)」 という注文方法です。
この2つを正しく理解しておくことは、投資初心者が失敗を避けるうえで欠かせません。
成行注文の特徴(すぐに売れるが価格指定できない)
成行注文は「値段を指定せず、今すぐ市場で売却する」という方法です。
注文が出た時点で、最も早く約定(取引成立)します。
メリットは すぐに現金化できること。特に急なニュースや暴落局面で「とにかく売りたい」というときに有効です。
一方で、どの価格で売れるか分からない ため、想定より安値で約定するリスクがあります。
指値注文の特徴(価格を指定できるが成立しない場合もある)
指値注文は「この価格になったら売る」と自分で条件を指定する方法です。
メリットは 思った価格で売却できる 点です。
例えば「株価が1,500円になったら売りたい」と設定すれば、それ以下では売却されません。
ただし、設定した価格に市場が届かないと いつまでも売れない可能性がある ことがデメリットです。
投資初心者が使いやすいのはどちらか?
投資初心者はまず 指値注文 を基本にするのがおすすめです。
理由は「想定外の安値で売ってしまう失敗」を防げるからです。
ただし、暴落や急変動の場面では売却できずに含み損が拡大するリスクがあるため、状況に応じて成行を使う柔軟さも必要です。
「普段は指値、緊急時は成行」 と覚えておくと実践的です。
私個人の意見
私は基本的に指値注文で売却をしています。
成行で思わぬ安値で約定して後悔した経験があるため。
ただし、暴落局面では「売れないまま株価がさらに下がる」リスクもあるので、その場合は迷わず成行を使うようにしています。
経験上、売却は状況に応じて成行と指値を使い分けるのが一番安全 だと感じています。
③ その他の注文方法(逆指値・OCO注文など)
成行注文や指値注文のほかにも、株を売却する際に活用できる注文方法があります。
これらをうまく使えば、投資初心者でもリスク管理や効率的な売買がしやすくなります。
逆指値注文で損切りを自動化
逆指値注文は「株価が○円以下になったら成行(または指値)で売却する」という仕組みです。
例えば株価1,500円で購入した株に「1,400円を下回ったら成行で売却」と設定しておけば、自動的に損切りが実行されます。
感情に左右されずに損失を限定できるため、損切りが苦手な投資初心者にとって有効な手段 です。
OCO注文で利益確定と損切りを同時に設定
OCO注文(オー・シー・オー注文)とは、2つの条件を同時に出して「どちらかが成立したらもう一方を取り消す」注文方法です。
例えば「1,600円で売却(利益確定)」と「1,400円で売却(損切り)」を同時に設定できます。
これにより、利益確定と損切りを両立させることができ、相場を見ていない間も安心感があります。
応用注文を使うメリットと注意点
逆指値やOCOは非常に便利ですが、証券会社によって利用できる注文方法が異なります。
また設定を誤ると意図しない価格で売却されるリスクもあるため、最初は少額で試して慣れるのがおすすめです。
応用注文を活用できるようになると、売却の自由度とリスク管理の幅が大きく広がるでしょう。
私個人の意見
私は短期投資をしていた頃、逆指値を入れずに含み損を膨らませた苦い経験が多々あり。
短期投資を中心に株式投資を行うときは「逆指値は保険」と考え、必ず設定することを強くおススメします。
またOCO注文は便利で、「利益を取りつつ、損も限定する」 という投資の理想形を実現できるのは頭の片隅に入れていてほしい。
④ NISA口座で株を売却する場合の注意点
新NISAの非課税枠の仕組み
2024年からNISAは大きく改正され、非課税投資枠が拡充されました。
-
成長投資枠:年間240万円、最大1,200万円
-
つみたて投資枠:年間120万円、最大600万円
合計で 年間360万円、最大1,800万円 まで非課税で投資できます。
さらに非課税期間は「無期限」となり、より長期投資に適した制度になりました。
売却後は非課税枠を再利用できる
旧NISAでは「一度使った枠は売却しても復活しない」という制約がありました。
しかし新NISAでは、売却すれば翌年にその分の非課税枠が再利用できる ようになりました。
これにより、柔軟に資産を入れ替えながら非課税の恩恵を受け続けることが可能になっています。
損益通算ができない点は変わらない
一方で注意すべきは、NISA口座では依然として損益通算ができない点です。
例えば特定口座で利益が出て、NISA口座で損失が出ても相殺できず、その損失は税制上「なかったこと」になってしまいます。
この特徴を理解せずに使うと、思ったより資産が増えにくいことがあります。
長期保有目的とのバランスを考える
NISAは制度改正によって柔軟性が高まりましたが、本来は長期的な資産形成を目的とした制度です。
短期的に売買を繰り返すよりも、「長期保有で非課税メリットを最大化する」 ことを基本方針にするのが賢明です。
私個人の意見
私も新NISAを活用していますが、非課税枠が売却後に翌年復活する点は非常に使いやすいと感じています。
ただし損益通算ができないため、NISAはあくまで「長期保有の資産枠」と割り切っています。
新NISAは“長期投資の強力な味方”であり、短期売買ではなく資産形成に集中させるべき口座 だと思います。
⑤ 特定口座で株を売却する場合の注意点
源泉徴収ありなら確定申告が不要
特定口座の「源泉徴収あり」を選ぶと、株を売却した際に発生する利益に対して税金(約20%)が自動で計算・徴収されます。
そのため、基本的に確定申告は不要で、投資初心者やサラリーマンに最も使いやすい仕組みです。
配当金も「源泉徴収ありの特定口座」にまとめることで、管理が非常に楽になります。
源泉徴収なしは確定申告が必要
一方で「源泉徴収なし」を選んだ場合は、年間の取引を証券会社が計算してくれるものの、確定申告を自分で行う必要があります。
節税や損益通算を意識して使う人もいますが、手間がかかるため投資初心者には不向きです。
損益通算や繰越控除が可能
特定口座の大きなメリットの一つが、損益通算や損失の繰越控除ができることです。
例えばA株で+30万円、B株で-20万円だった場合、利益と損失を合算して+10万円として課税されます。
また損失が出ても翌年以降3年間まで繰り越して控除できるため、安定した税務上のメリットがあります。
投資初心者は「源泉徴収あり」を選ぶのが無難
確定申告の負担を避けつつ、損益通算や繰越控除のメリットを享受できるのが「源泉徴収あり」の特定口座です。
株式投資を始めるサラリーマンの多くがこの方法を選んでおり、安心して投資を続ける基盤となります。
私個人の意見
私は特定口座(源泉徴収あり)を利用しています。
理由はシンプルで、税金処理をすべて自動でやってくれるから。
サラリーマンとして働きながら株式投資をしていると、確定申告の手間を減らせるのは大きなメリットです。
さらに、もし特定口座(源泉徴収あり)を選ばずに確定申告すると、総合課税の対象となり、給与所得が多い人ほど税負担が増えるリスク があります。
このリスクをなくすためにも、特定口座(源泉徴収あり)を選ぶのが最も無難で安心な方法だと思います。
⑥ 投資初心者がやりがちな売却の失敗例
成行で思わぬ安値売却をしてしまう
投資初心者がよくやってしまうのが、「とにかく売りたい」と焦って成行注文を出すことです。
成行はすぐに約定する一方で、板の状況によっては思った以上に安値で売却されるリスクがあります。
特に流動性が低い銘柄(一日の出来高が1000株など売買が少ない)では注意が必要です。
指値にこだわりすぎて売れないまま株価が下がる
逆に「この価格でなければ売らない」と指値に固執すると、株価がその水準に届かず売却できないまま下落してしまうことがあります。
結果として、売り時を逃し含み損が拡大してしまうケースも多いです。
**「利益確定も損切りも、欲を出しすぎない」**ことが大切です。
NISAで損益通算ができないことを知らずに損失を拡大
新NISAでは売却益が非課税になる一方で、損失を他の利益と相殺できないという特徴があります。
この仕組みを理解せずにNISAで短期売買を繰り返すと、「特定口座の利益にだけ課税され、NISAの損失は救済されない」という状況になり、思った以上に不利になることがあります。
私個人の意見
私も投資を始めた頃、指値にこだわりすぎて売却できず、その後の下落で損失を広げた経験あり。
また、NISAでの損益通算ができないことを軽く見て取引した結果、税金面で損をしたこともありました。
経験から学んだのは、「売却は欲と無知が最大の敵」 ということです。
投資初心者はまず、基本的な仕組みを理解し、ルールを守って取引することが失敗を防ぐ一番の近道だと思います。
⑦ まとめ|正しい売却方法を理解して安心して投資を続けよう
株の売却は単なる「現金化の操作」ではなく、投資成果を大きく左右する重要なプロセスです。
成行や指値といった基本的な注文方法を理解し、逆指値やOCOなどの応用注文も活用すれば、リスクを抑えた効率的な取引が可能になります。
また、口座の種類による税制の違い も見逃せません。
-
NISA口座は非課税のメリットが大きいが、損益通算できない点に注意
-
特定口座(源泉徴収あり)は税金処理を自動化でき、サラリーマンや投資初心者に最適
-
一般口座は計算や確定申告が煩雑なため、選ぶメリットはほとんどない
投資初心者がやりがちな失敗は「欲や感情に振り回されること」と「仕組みを理解しないまま取引すること」です。
売却のルールを学び、口座や注文方法の特徴を把握しておくことで、安心して投資を続けられるようになります。
私個人の意見
私はこれまでの経験から、「売り方を理解していないと利益は守れない」 と痛感しました。
特に特定口座(源泉徴収あり)を利用してからは税務の不安がなくなり、売却に集中できるようになりました。
投資は「買うこと」よりも「どう売るか」で成果が変わる──これは実体験からも間違いないと断言できます。