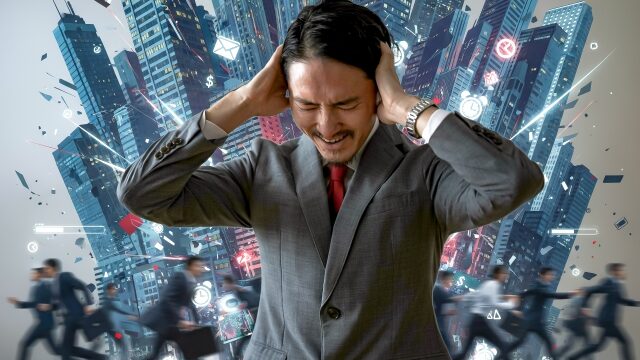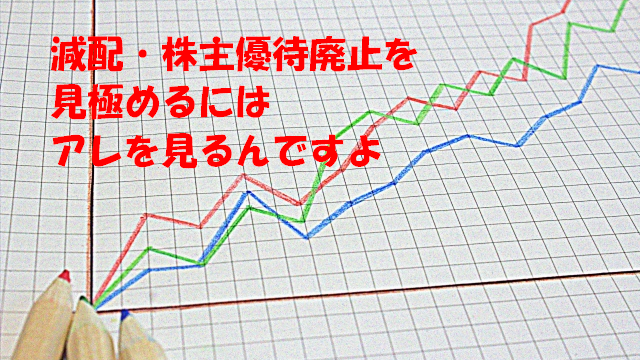株主優待はもらった後が大事!利回りと使いやすさで選ぶ賢い優待生活

「株主優待、もらえるだけでお得!」
確かにその通り。でも実は、“もらって終わり”では非常にもったいないんです
なぜなら、優待には「使いやすさ」や「利回りの高さ」に大きな差があり、
選び方ひとつで実質利回りが何倍にもなることもあるからです
本記事では、株主優待を「もらって終わり」にしないために、
-
利回りだけで選ぶと危ないワケ
-
使い勝手のよい優待・使いづらい優待の違い
-
生活コストを下げる“賢い優待生活”の始め方
などを、株初心者にもわかりやすく解説します
すでに優待をもらっている人も、これから優待投資を始めたい人も、
**“もらったあとで後悔しないための知識”**をぜひ身につけてください!
① 株主優待は「もらって終わり」じゃもったいない!
株主優待をもらった瞬間、嬉しくてついSNSに投稿したり、家族と話題にしたり…
でもその後、こういう経験はありませんか?
-
「思ったより使い道がなくて、結局放置…」
-
「期限が切れてしまった」
-
「使うために、わざわざ行くのが面倒だった」
そう、株主優待は“もらったあと”が本当の勝負なんです。
配当と違って、株主優待は使って初めて“お得”になる仕組み。
逆に言えば、使いづらければただの自己満足で終わってしまうこともありま。
本記事では、そんな「もらったあとの失敗」を防ぐために、
-
利回りだけで選んでいませんか?
-
ちゃんと使いこなせる優待ですか?
-
生活にどれだけ役立っていますか?
という観点から、“使って得する”優待投資の考え方をわかりやすく解説していきます
② 利回りだけで選ぶと後悔する理由
株主優待の銘柄を選ぶとき、
「優待+配当で総合利回り5%超!」といった数字に惹かれることはありませんか?
確かに、数字だけ見ると「お得そう」に感じます
でも――その優待、実際に使えますか?
たとえば…
-
地方にしかない店舗でしか使えない外食券
-
自社サイトでしか注文できない商品セット
-
有効期限が短く、使い切れない優待券
こういった株主優待は、使わずに終わってしまう可能性が高いです。
結果として、「総合利回り5%」と表記されていても、実際の“恩恵”はゼロ、なんてことも 汗
株主優待の総合利回りを計算して次に考えることは、
**「金券換算できるか」「使いやすいか」「無駄なく使い切れるか」**をしっかり考慮すべきです
実質利回りを高く見せるだけの**“見せかけ優待”に騙されないようにしましょう。**
📌 関連記事もぜひ参考に:
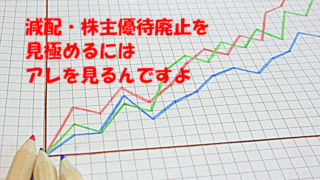
③ 実際に役立つ!使いやすい株主優待の特徴とは?
では、どんな株主優待が「実際に使えてお得」と言えるのでしょうか?
ここでは、実際に私も日々の生活で活用している“使いやすい株主優待”の特徴を紹介します
✅ 全国どこでも使える汎用性の高い優待
-
クオカード(QUOカード)
-
VisaやJCBのギフトカード
-
楽天ポイント・PayPayポイントなどの電子マネー
これらは金券としてコンビニやスーパーなど日常の買い物にそのまま使えるため、非常に利便性が高いです
「生活費の一部を株主優待でカバーできる」=実質利回りが上がるとも言えます
✅ 自社商品券でも使いやすいタイプ
たとえば以下のような外食・小売系の優待は人気です
-
イオン、サンマルク、王将、三越伊勢丹、Jフロントなど こちらは買い物金額の10%など割引あり、イオンの場合はキャッシュバックなどり、実際に日常生活に役立つ優待です
-
吉野家、すかいらーく、マクドナルド、クリエイトレストランツ、コメダHD これらは家族で外食に使える・店舗数が多い・1,000円〜3,000円で気軽に使いやすいですね
✅ 食料品・日用品など“消耗品系”も実用性が高い
-
トイレットペーパーやティッシュ、衛生用品などの日用品(例:日本紙パルプ商事、ライオン)
-
自社商品(例:理研ビタミン)
-
自社商品のお菓子セット(例:江崎グリコ、正栄食品工業)
これらは、**「日常的に必ず消費するもの」や「買うと意外と高くつくもの」**が対象なので、
家庭の出費を確実にカバーできる“実用的な株主優待”と言えます
特に日用品系の株主優待は賞味期限や保管スペースの心配も少なく、安定した人気あり
企業としても継続しやすいため、「優待廃止リスクが低い」という点でも安心です
💡優待の総合利回りの数字に惑わされず、「実際にどれだけ使えるか?」という視点を持つことが、優待選びの成功ポイントです
④ 注意!“使いづらい”株主優待の典型パターン
一見お得そうに見える株主優待でも、実際に使ってみると「これはちょっと…」と思うケースがあります
ここでは、「使いづらい」と感じやすい株主優待の典型パターンを紹介します
❌ 地方限定・店舗が少ない
たとえば、特定の地域にしか店舗がない飲食店やスーパーの優待
地方在住者や都市部の一部しか使えないものは、使える人が限られてしまいがちです
-
例:関西ローカルの外食チェーン、北海道限定の流通店舗など
→ 金券としての価値はあっても、「行けない」「使えない」=実質ゼロになることも
※ヤフオクやメルカリで「売る」といった考えもありますが、手間を考えると…
❌ 有効期限が極端に短い/利用条件が厳しい
-
2か月以内に使わなければならない
-
「〇円以上の買い物で1枚のみ使用可」といった制限つき
-
オンラインでの事前申請が必要で手間がかかる
こういった優待は、気づいたら期限切れ/条件が面倒で放置といった“優待ロス”を招きやすく、結果として損失になりかねません
❌ 自社製品の詰め合わせ(ニッチすぎる)
企業によっては、株主優待として自社製品の詰め合わせを贈るケースがありますが…
-
味の好みが合わない(調味料、レトルト)
-
使い方がわからない(化粧品、健康食品)
-
そもそも使わない(業務用食品や特殊工具など)
このような場合、タンスの肥やしになり部屋の場所をとるだけです
金額換算はできても、**「実際に使えない=利回りゼロ」**と割り切る視点も必要じゃないかな
✅ 判断基準のヒント
使いやすいかどうか迷ったら、以下の3点でチェックしてみてください:
-
全国で使える?
-
期限は3か月以上ある?
-
“自分が普段お金を払って買っているもの”に近い?
⑤ 実際にやってみた!優待活用の具体例
ここでは、筆者である私が実際に取得・活用している株主優待の具体例を紹介します
机上の話ではなく、リアルな活用事例があれば、あなたも「自分にもできそう」と感じてもらえるかも
🍴 外食優待で月1回の外食代が“ぐ~ンとお得に”
我が家では、すかいらーくやイートアンドなどの外食系優待を活用して、
月1回の家族の外食を“株主優待”でまかなっています
これらは2000円分などの食事優待券が届きます
「今日は株主優待で外食にしようか」というちょっとした楽しみ、そして支払いの時に「株主様いつもありがとうございます」と言われるときもあり
その時はちょっといい気分になりますよ 笑
🛍️ イオンのキャッシュバック優待は生活に直結
イオン(8267)の株主優待である「オーナーズカード」は、買い物金額の3%がキャッシュバックされます(300株保有時)
日常の買い物がイオン中心の家庭にとっては、現金値引きと同じ効果があり、
節約というより“収入感覚”で得を実感できますよ
🎁 お菓子や日用品の優待で「買わずに済むもの」が増えた
正栄食品工業(8079)やライオン(4912)のような企業の優待は、
“自社製品の詰め合わせ”が届きます。
-
クッキーやチョコレート、おつまみなど(正栄食品)
-
ハンドソープ、洗剤、歯磨き粉などの日用品(ライオン)
「あ、これちょうど買おうと思ってた!」というタイミングで届くこともあり、
特にライオンは新製品なども入って、毎年贈られてくるのが異なるので今回の中身はなんだろう?と楽しみにもなりますね
使ってヨシ、渡して喜ばれるもの
これは個人投資家に大人気の日本マクドナルドホールディングス(2702)自分や家族で使うのはもちろんですが、人に渡すと本当に喜ばれます。
だから我が家ではすべて使わず、知人や友人から物をもらった時の返礼品として渡しています。
無償で高価なものを手に入れてしかも相手に喜ばれる。これ本当におすすめですよ!
📦 株主優待の管理は“エクセル管理”が便利
複数銘柄を持ち始めると、
「いつ届く?」「何がもらえる?」「使用期限は?」がごちゃごちゃに
私は簡単なExcel表で、
-
優待内容
-
権利確定月
-
到着時期
-
使用期限
-
実質利回り
などを記録しておくことで、もらい忘れ・使い忘れをゼロにするよう気を付けています
📌 優待は“受け取って終わり”ではなく、
**「生活にどう活かすか」「どれだけ出費を減らせるか」**が大切です!
⑥ まとめ|株主優待は“使いこなしてこそ”価値がある
株主優待は、「もらって満足」で終わらせてしまっては非常にもったいない制度
せっかく手に入れた優待も、使いづらければ実質“利回りゼロ”になることもあります
本記事では、
-
利回りだけで選ぶことの落とし穴
-
実際に役立つ“使いやすい優待”の特徴
-
使いづらい典型的なパターン
-
生活に活かすリアルな活用例
を通じて、**「優待は選び方・使い方しだいで“家計の強い味方”になる」**ということをお伝えしてきました
✨ 最後に、もう一度お伝えしたいこと
-
株主優待は“もらった後”の使い方が重要!
-
自分や家族が“ちゃんと使えるかどうか”を基準に選ぶべき
-
優待利回りより“生活の中でどれだけ役立つか”を重視すること
もし、これから優待銘柄を選ぶなら、
「利回りが高いから」「有名だから」ではなく、
“自分にとって本当に価値のある優待か?”という視点を持って選んでみてください
その一つひとつの選択が、あなたの投資生活をより豊かに、そして楽しくしてくれるはずです