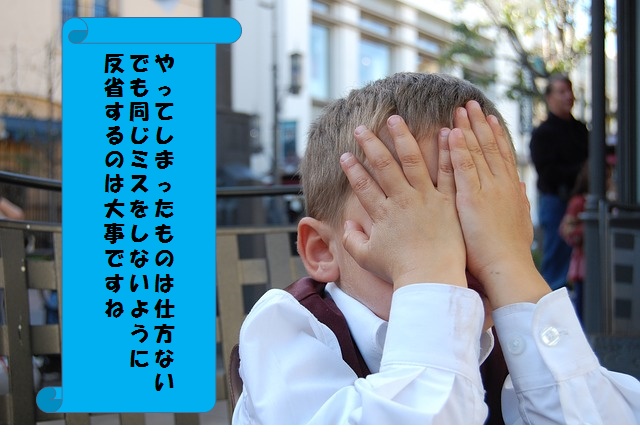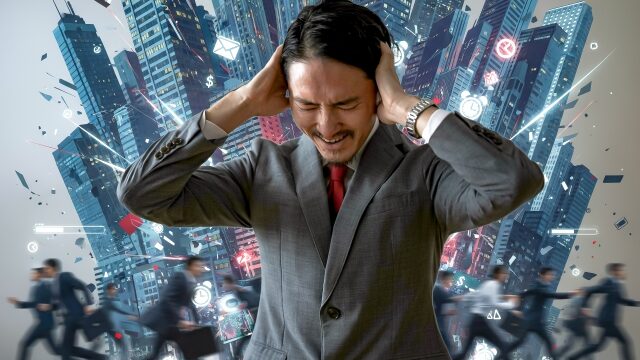【2025年版】株・FXの税金対策完全ガイド|利益が出た人が今すぐやるべき節税術

「今年は株やFXで利益が出たけど…このまま税金を払うのはもったいない気がする」
そんな風に感じていませんか?
実は、株式投資やFXで得た利益には、上手に使えば節税につながる制度がいくつも存在します。
たとえば、
-
「損益通算」や「繰越控除」で、払いすぎた税金を取り戻す
-
「所得区分」を理解して、無駄な確定申告を避ける
-
「ふるさと納税」「iDeCo」「医療費控除」などを活用し、投資以外でも節税
など、知っているかどうかだけで何万円も差が出るのが、投資と税金の世界です。
このブログでは、
株・FXで利益が出た人がやるべき2025年最新版の節税対策を、FP資格保有者である筆者が実体験を交えてわかりやすく解説します。
「知らずに損したくない」
「どうせなら手元に残るお金を増やしたい」
そんな方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
“納税額を減らす第一歩”が、ここから始まりますよ。
① 投資の利益にかかる税金の仕組みとは?【株・FXの所得区分を理解しよう】
「利益が出たら、税金ってどれくらい取られるの?」
投資初心者の多くが気になるこの疑問。実は投資の種類によって、課税される「所得の区分」や「税率」が異なるのです。
ここでは、まず株式とFXで利益が出た場合に、どのような税金がかかるのかをわかりやすく解説します。
■ 株式投資の利益は「譲渡所得(分離課税)」に分類
株を売って得た利益(=キャピタルゲイン)は「譲渡所得」に該当します。
これは申告分離課税という形で扱われ、**一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)**の税金がかかります。
また、配当金を受け取った場合は「配当所得」となり、以下のように課税されます。
| 配当金の受け取り方法 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉あり) | 20.315% | 自動的に源泉徴収され、確定申告不要 |
| 一般口座 or 確定申告 | 総合課税 or 申告分離課税 | 配当控除を使えるケースもあり |
■ FXの利益は「雑所得」に分類される(少しややこしい)
FXで得た利益は、基本的に**雑所得(申告分離課税)です。
税率は同じく20.315%**ですが、株との違いとして「損益通算できる範囲」や「所得区分の扱い」に注意が必要です。
| FXの種類 | 所得区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 国内FX業者(くりっく365含む) | 雑所得(申告分離課税) | 他の雑所得とは通算不可。FX同士のみ通算可能 |
| 海外FX業者 | 雑所得(総合課税) | 累進課税(最大55%)になる可能性も |
■ 特定口座(源泉あり)にしておけば確定申告は不要
株や投資信託の場合、「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいれば、確定申告をしなくてもOKです。
一方、
-
複数口座の損益通算をしたい
-
繰越控除を使いたい
-
iDeCoやふるさと納税などで控除を受けたい
といったケースでは、確定申告をすることで税金を減らせるチャンスが生まれます。
▼ ここでのポイント
-
株とFXでは「所得区分」が違うため、節税の方法も異なる
-
税率は基本20.315%(海外FXを除く)
-
確定申告が不要でも、した方が得になるケースが多い
② 知らなきゃ損!まずは「損益通算」と「繰越控除」を理解しよう
投資で利益が出た人にとって、**節税の第一歩は「損益通算」と「繰越控除」**を正しく理解することです。
どちらも確定申告によって適用でき、支払う税金を大きく減らせるチャンスになります。
■ 損益通算とは?証券口座ごとの損益を相殺して節税!
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
-
SBI証券で+50万円の利益
-
楽天証券で−30万円の損失
この場合、損益通算を行えば、50万円 − 30万円 = +20万円が実際の課税対象となります。
株式投資で発生する税金は、一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)。
つまり、確定申告をして損益通算すれば、約6万円(=30万円×20.315%)もの税金を抑えることができるわけです。
✅ 確定申告なしだと…
50万円に対して課税 → 税金 約10万円
✅ 確定申告ありだと…
通算後の20万円に対して課税 → 税金 約4万円
→ 約6万円も節税!
■ 同じ証券会社なら自動で損益通算される
たとえば、SBI証券でA株が+30万円、B株が−20万円という場合、同じ証券会社内なら自動的に損益通算されます。
「特定口座(源泉徴収あり)」を利用していれば、証券会社が自動で税金を計算・徴収してくれるので、確定申告をしなくてもOKです。
■ 異なる証券会社を使っている人は要注意!
問題は、異なる証券会社を使っていて、一方は利益、一方は損失というケースです。
この場合、自動で損益通算はされません。
自分で確定申告をして、両社の「特定口座年間取引報告書」を提出しなければ、損失が考慮されず、税金を余計に支払ってしまうことになります。
複数口座を使っている人ほど、確定申告で損益通算することで節税インパクトが大きくなる可能性があります。
■ 所得区分に注意!株とFXは通算できない
損益通算ができるのは、同じ所得区分(課税方式)内の金融商品に限られます。
| 所得区分 | 対象 | 通算可能か |
|---|---|---|
| 譲渡所得 | 株式、投資信託、ETFなど | ✅ 可能 |
| 雑所得(申告分離) | 国内FX(店頭) | ✅ FX同士で可能 |
| 総合課税 | 海外FX、仮想通貨など | ❌ 不可(原則) |
つまり、株とFXは原則通算できないため、それぞれ別に課税されます。
■ 繰越控除とは?損失を3年間繰り越して節税できる制度
損益通算をしても差し引きで損失が残ってしまった場合、その損失を「翌年以降の利益と相殺できる」のが繰越控除です。
これも確定申告をすることで活用できます。
▼ たとえば、こんなケース:
-
2024年:−50万円の損失
-
2025年:+30万円の利益
-
2026年:+40万円の利益
上記のように、2024年に損失が出たとしても、確定申告をしておけば…
-
2025年の30万円の利益 → 全額非課税(損失と相殺)
-
2026年は残りの損失20万円を控除可能 → 実質+20万円のみ課税対象
というように、損した年に確定申告しておくことで、未来の税負担を抑えることができるのです。
▼ ポイントまとめ
-
対象は「譲渡所得」=株式や投資信託など
-
最大3年間、損失を繰り越して節税できる
-
1年でも確定申告を忘れると無効になるので注意!
✅ 重要!
「繰越控除」を受けるには、損失が出た年から毎年継続して確定申告することが必須です。
1年でも申告を忘れると、その年以降の控除は無効になります。
損失が出てしまった年でも、あきらめずに確定申告をしておくことで、翌年以降の節税につながるチャンスになります。
株式投資やFXは、“勝つ年”と“負ける年”が混在するからこそ、この制度を上手く使いこなすことが大切ですよ。
③ 投資の税額には直接影響しない。でも“あなたの税金”は減らせる節税制度
「ふるさと納税やiDeCoを使えば、株やFXの税金が下がるんですよね?」
そう考える方も多いですが、実は “直接は関係ありません”。
なぜなら、株やFXで得た利益(譲渡益や為替差益)は、申告分離課税に分類され、
ふるさと納税・iDeCo・医療費控除などの“所得控除”や“税額控除”が適用される「総合課税」とは切り離されて課税されるためです。
では、なぜ使う価値があるのか?
それは、あなたが支払う「他の税金」を下げられるからです。
たとえば、給与や副業収入などを得ている人が投資でも利益を出した場合、
全体として課税対象となる「所得」が多くなるため、住民税・所得税の税率が上がる可能性があります。
つまり、株・FXの税金には影響しなくても、あなたの総合的な税負担を軽減する手段としては有効というわけです。
▼ 節税につながる代表的な制度
| 制度 | 節税のしくみ | 対象所得 | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| ふるさと納税 | 税額控除 | 所得税・住民税(総合課税) | 実質2,000円で返礼品+税負担軽減 |
| iDeCo | 所得控除 | 総合課税所得 | 掛金全額が所得控除、最大数万円の節税 |
| 医療費控除 | 所得控除 | 総合課税所得 | 高額医療費の年は特に効果大 |
✅ ポイントまとめ:
-
株やFXの税金(申告分離課税)は別枠の計算
-
でも、給与・副業などの総合課税所得が多くなると、その分の税金が増える
-
だからこそ、ふるさと納税・iDeCo・医療費控除などを併用して、「トータルの納税額」を抑えることが重要
このように、投資利益に直接効く制度ではありませんが、
税金全体を下げて“実質手取りを増やす”ために活用すべき制度として、しっかり押さえておきたいところです。
④ 知らないと損!「申告分離課税」と「総合課税」の違いとは?
税金対策を考えるうえで、「自分の所得がどの課税方式に当てはまるか?」を理解しておくことはとても重要です。
特に、**株やFXの利益は“申告分離課税”**という仕組みで課税されるため、他の所得(給与や副業など)とは分けて計算されます。
ここでは、申告分離課税と総合課税の違いをわかりやすく整理します。
■ 申告分離課税とは?
株式の売買益や配当、FXで得た利益などに適用される課税方式です。
他の所得とは“完全に分離”して計算され、税率も一律で決まっています。
-
税率は一律 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
-
所得がいくら増えても、税率は変わらない
-
他の所得と“損益通算”はできない(※株とFXの間では通算不可)
【該当するもの】
-
上場株式の譲渡益(売買益)
-
上場株の配当金(※特定口座の「源泉徴収あり」の場合)
-
FX(外国為替証拠金取引)の利益 など
■ 総合課税とは?
給与や副業、年金、事業所得などが対象となり、すべての所得を合計して税額を決める課税方式です。
**所得が増えれば税率も上がる「累進課税制度」**が適用されます。
-
所得に応じて税率は5%~45%
-
**所得控除(iDeCo・医療費・ふるさと納税など)**の対象になる
-
家族構成や扶養状況などによって税額が変わる
【該当するもの】
-
給与所得
-
事業所得
-
不動産所得
-
一時所得、雑所得(副業・アフィリエイトなど)など
■ この違いを理解しておくメリット
投資に関する税制は、「投資家全体に公平に、かつシンプルに課税される」ことを重視しており、分離課税を採用しています。
逆に、総合課税の対象となる収入は控除や軽減策が多く、節税の幅が広いため、
「投資以外の所得でどれだけ対策できるか」が、トータルの税負担を左右するカギになります。
✅ ポイントまとめ
-
株・FXの利益=申告分離課税(一定税率)で独立した課税枠
-
給与・副業・医療費・ふるさと納税=総合課税枠に影響
-
節税を考えるときは、「自分の収入がどちらの課税枠なのか」を理解することが第一歩!
⑤ 法人口座や海外口座って節税になる?やってはいけない危険な節税
「法人化すれば税金を減らせる」
「海外口座なら税率が低くてお得」
そんな話を耳にしたことはありませんか?
確かに一部は事実ですが、知識なく手を出すと“危険な節税”に転落する可能性が高いです。
● 節税目的だけの“法人化”はむしろ損することも
法人を設立すれば、経費計上の幅が広がったり、所得税よりも法人税率の方が低く済むケースもあります。
ただしこれは、以下のような前提があってこそ効果があるものです:
-
投資で安定して継続的に利益を出している
-
トレードがほぼ本業になっている
-
法人運営コスト(会計・税務・登記など)に見合うだけのリターンがある
逆に、副業レベルで年数回しか売買しない、利益もまだ安定していない――といった方が法人化しても、コストばかりが増えて結局損をしてしまうことになります。
● 海外FX・海外証券口座の“税制と出金リスク”に要注意!
「海外なら税金が安い」「ハイレバレッジで稼げる」といった理由で、海外FXや海外証券口座を使う方もいますが、かなりのリスクを伴います。
税務面でのリスク:
-
海外FXは総合課税扱い(最大税率55%)となることも
-
確定申告しなければ脱税扱いになるリスク
-
日本国内と異なる税務ルール(損益通算や繰越控除が使えない)
実務面でのリスク:
-
出金時にトラブルが発生することが多い
-
サポートが英語のみ、連絡がつかない
-
国内銀行口座への入金が遅れる、拒否される
-
出金できたとしても、“資金洗浄”の疑いで凍結されるケースもあり
実際に「大きく利益が出たのに、出金しようとしたらできなかった」という声も多数あり、私は海外口座での運用はおすすめしません。
● 脱税と節税は紙一重。だから“プロに相談を”
「経費にできると思った」
「海外だからバレないと思った」
という安易な考えが、脱税と見なされる可能性もあります。
税務調査では過去にさかのぼって指摘されることもあり、延滞税・加算税などを含めて大きな損失になるケースも少なくありません。
節税を成功させたいなら、「税理士やFPなどの専門家に相談する」ことが最も安全で、最も効果的な方法です。
⑥ 知らないと損する実例|“税金で損した”投資家と“得した”投資家の違い(修正版)
投資で得た利益は、税金の知識ひとつで「手元に残るお金」が大きく変わります。
ここでは、実際によくある「やって損した」「知って得した」投資家の違いを紹介します。
● 損益通算しなかったAさん|納税額が30万円も増加…
Aさんは、A証券で+50万円、B証券で−20万円の収支がありました。
しかし、複数の証券会社を使っていたことにより損益通算されないことに気づかず、確定申告を行いませんでした。
その結果、50万円の利益に対して約15万円の税金を支払うことに…。
本来であれば、確定申告をしていれば「50万円−20万円=30万円」に抑えられ、税額は約9万円程度で済んだのです。
このように、損益通算は「確定申告しなければ適用されないケース」があるため注意が必要です。
🔍 損益通算できるのは、株式・投資信託・ETFなど同じ区分(申告分離課税)内の利益と損失に限られます。
FXや先物取引とは通算できない点も忘れずに。
● 繰越控除を忘れていたCさん|翌年になって大後悔…
Cさんは、2023年に−80万円の損失を出したものの、「確定申告が面倒」と思い何もしませんでした。
しかし翌年2024年、+100万円の利益が出たことで…
なんと100万円に対してそのまま課税対象となってしまいました。
本来であれば、「前年の−80万円」を損失繰越控除で差し引くことで、20万円分にだけ課税されるはずでした。
結果的に、10万円以上の納税差が出てしまったのです。
🔁 繰越控除は最大3年間可能ですが、初年度に確定申告をしていないと無効になります。
損失が出た年こそ「放置せずに申告」が鉄則です。
● 小さな差が、大きな差になる
税金のルールを知らないだけで、数万円〜十数万円の差が生じるのが投資の世界。
-
「損益通算しないまま放置」
-
「繰越控除のチャンスを逃す」
-
「税制上の区分を理解せず申告漏れ」
これらの“見えない失敗”は、あとで気づいても取り返しがつかないことが多いのです。
⑦ FPが教える!投資家ができる節税の“最適な順番”とチェックリスト
「節税」と聞くと複雑で難しそうに思うかもしれませんが、実は多くの節税対策は順番と準備がすべてです。
ここでは、FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から、投資家が無理なく節税できるための具体的な手順と習慣を解説します。
◆ 節税対策をやるべき「順番」
① 年内に利益と損失の見直しをする(損出し含む)
→ 利益確定の予定がある人は、含み損を抱えた銘柄を年内に売却することで、損益通算の効果を最大限に。
② 年末までに損失が出た場合は“必ず”確定申告を準備
→ 損失繰越控除を使うには、最初の年に申告しないと無効になります。
③ 取引証券会社を複数使っているなら損益通算を手動申請
→ 特定口座で自動計算されるとは限らないため、各社の年間取引報告書を確認して確定申告へ。
④ “合法的な節税制度”の活用も検討
→ 投資による節税ではなく、自身の所得圧縮の手段として、
・ふるさと納税
・iDeCo
・医療費控除(10万円超えた分)
・住宅ローン控除 などをフル活用。
◆ 確定申告に向けて準備するべきこと
-
各証券会社からの「年間取引報告書」の保管(1月下旬〜2月上旬に届きます)
-
医療費の領収証(家族全体で10万円超える場合)
-
ふるさと納税の寄附証明書(自治体から送付)
-
iDeCoの掛金証明書(年末に郵送されます)
-
その他控除の対象になるものの確認
💡【ヒント】
国税庁の「確定申告書作成コーナー」は、わかりやすいUIで初心者でも入力しやすくなっています。
利用すれば、ミスを減らして時短にもつながります。
📚【補足】
確定申告の流れや記載例をわかりやすく知りたい人には、**ダイヤモンドZAI(毎年3月号)**が特におすすめです。
その年の法改正などにも対応しており、実際の画面付きで解説されているので、はじめての人にも親切です。
◆ 節税できる人がやっている“たった3つの習慣”
-
年末に「利益と損失のバランス」を確認するクセがある
-
取引記録や書類をこまめに整理し、確定申告を“怖がらない”
-
制度を“なんとなく”ではなく“数字”で理解している
節税も投資と同じく、「正しく知り、継続すること」が成果を生みます。
一度慣れれば、毎年の手続きは確実にスムーズに。
それによって「納めすぎ」を防ぎ、“利益を守る”もう一つの武器にすることができるのです。
番外編|“経費”を活用した節税も可能!副業投資家が知っておきたい項目
ここまでご紹介した節税策は、誰でも取り入れやすい“基本編”でしたが、実はもっと深く節税をしたい方には「経費活用」という選択肢もあります。
もしあなたが「副業として投資をしている」「ブログや情報発信もしている」「開業届を出して個人事業主として届け出ている」という場合は、一部の支出を「必要経費」として計上することができ、課税所得を下げて節税につながる可能性があります。
以下は、実際に多くの投資系個人事業主が計上している経費の一例です:
✅ 投資・副業に関連して認められることの多い経費例
-
家賃の一部(例:自宅の一室を執務スペースとして使っている場合)
-
スマホ・インターネット代(仕事にも使用している場合は按分して計上)
-
株式投資やFX関連の書籍・有料メディア購読費
-
情報収集や研究のための交通費(例:IRセミナー・株主総会出席など)
-
関係者との打ち合わせ・会食費(「投資情報交換の打ち合わせ」などの記録が必要)
これらの支出は、**「事業の遂行に必要であったこと」**が合理的に説明できれば、税務上の経費として認められる可能性があります。
⚠️ 注意点:すべての人に適用できるわけではありません!
ただし、以下の点には注意してください。
-
投資が完全に趣味レベルであったり、開業届を出していない方は、経費としての扱いが難しいことがあります。
-
家族との食事など、明確なビジネス目的が説明できない支出は経費として否認されるリスクもあります。
-
領収書や記録を残すなど、しっかりした証拠を残すことが大前提です。
💡 不安がある場合は「税理士への相談」も有効
「どこまで経費としてOKなのか、自分だけでは判断が難しい…」
そんなときは、信頼できる税理士へ一度相談してみるのがおすすめです。
最近では、投資や副業に特化したフリーランス向け税理士サービスなども充実してきており、無料相談からスタートできるところもあります。
このように、“必要な支出”をしながら節税もできるのが経費活用の強み。
本格的に投資を続けていく予定がある方にとっては、検討してみる価値は十分にあるでしょう。
⑧ まとめ|利益を守るのも立派な投資術。税金の知識は“最強の防御”
株式投資やFXで「利益を出すこと」ばかりに注目しがちですが、本当に重要なのは“利益を守ること”。
つまり、無駄な税金を払いすぎないための知識と準備こそが、あなたの資産を守り増やす“防御力”になるのです。
本記事でご紹介した内容は、すべて合法的にできる正しい節税方法です:
-
損益通算・繰越控除による税額圧縮
-
分離課税の理解と、節税制度(ふるさと納税やiDeCoなど)の併用
-
怪しい節税には手を出さず、正攻法で守る
-
副業や事業化による“経費活用”という次のステップ
税金対策を知っているかどうかで、「手元に残るお金」が大きく変わります。
「まだ利益がそんなに出ていないから関係ない」
そう思っている方も、いざという時に慌てないために、今から知っておくべき内容ばかりです。
✅ 確定申告で困らないために
確定申告書の作成や記入方法について不安がある方は、毎年発売される【ダイヤモンドZAI 3月号】が特におすすめです。
その年の最新制度に対応した、わかりやすい特集が組まれており、初心者でも安心して準備ができますよ。
あなたの投資利益を無駄にしないためにも、ぜひ「節税=守りの投資術」を今日から意識してみてください。
そして、得たお金を次の投資につなげていく――それが“賢い投資家”への第一歩です。